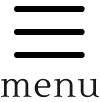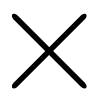ブログ
- 2025-06(6)
- 2025-05(4)
- 2025-04(1)
- 2024-06(1)
- 2024-04(2)
- 2023-12(2)
- 2023-11(1)
- 2023-07(2)
- 2023-05(1)
- 2023-03(1)
- 2023-02(3)
- 2023-01(2)
- 2022-12(1)
- 2022-11(1)
- 2022-09(2)
- 2022-07(1)
- 2022-06(2)
- 2022-05(1)
- 2022-04(2)
- 2022-03(2)
- 2022-02(2)
- 2022-01(1)
- 2021-12(3)
- 2021-11(3)
- 2021-09(2)
- 2021-07(1)
- 2021-06(2)
- 2021-03(1)
- 2020-12(10)
- 2020-09(1)
- 2020-08(1)
- 2020-06(1)
- 2020-05(2)
- 2020-04(1)
- 2019-11(1)
- 2019-10(3)
2021/11/12
ワークショップのお知らせ

こんにちは。Tukuroi(妻)です。
家具のリペアやメンテナンスを暮らしの一部に取り入れていけたら良いな、という思いから始まったワークショップ。
第2回目の内容はずっとやりたいと思っていた内容、椅子の「ソープメンテナンス」です。
やりたかった理由として、張替修理でお預かりすることが多い椅子の中に「Yチェア」があります。
お預かりするものは、15年~20年くらい使用された状態のものが多いです。
ほとんどのものがフレームのメンテナンスを一度もされることなく経年変化が進み、シミや汚れが目立つ状態になっています。
(写真下/使用して15年ほど経過したビーチ材のYチェア)
椅子は使用頻度が高い家具で、特に食事する時に使う椅子はどうしても汚れやすくなります。
でも忙しい日々の中で家具のメンテナンスをすることにハードルを感じていたり、シミや汚れは気になっているけど、メンテナンス方法が分からない、という方もいらっしゃると思います。
実は「ソープメンテナンス」という方法で自宅でも気軽にお手入れが出来るのです。
「ソープメンテナンス」とは、「ソープ仕上げ」「オイル仕上げ」の家具に行えるメンテナンス方法で、石けんの泡を使って汚れを落とす方法です。
石けんで洗うの?と驚かれる方もいらっしゃるかもしれませんが、肌と一緒で石けんの泡で汚れを浮かして落とす、という原理です。
とても簡単に行える上に、使う道具が身近にあるもので出来てしまいます。
無添加の石けんを使うので、害もなく片付けも楽なのです!
小さなお子様にも安心してお手伝いしてもらえますね。
ソープメンテナンスで取り切れない汚れもありますが、乾いた後にサンドペーパーで少し研磨して仕上げると手触りも良くなり、キレイに仕上がります。
(写真下/上がメンテナンス前、下がメンテナンス後)
お持ちの椅子で、メンテナンスをしたかった!という方や年末の大掃除の一環としてメンテナンスしてみようかな?という方はぜひ下記のワークショップ概要をご覧ください!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 ソープメンテナンスのワークショップ】
○Yチェア等の椅子のフレーム木部をソープメンテナンスでお手入れします。
開催日 11月23日(火・祝)
開催時間 10時から11時30分くらい
料金 1,000円
定員 6名
(ご家族等、複数名でご参加されたい方はお知らせください。お子様も大歓迎です!)
○「Yチェア」やその他、「ソープ仕上げ」「オイル仕上げ」の椅子をお持ちの方を対象とさせていただきます。
○メンテナンスしたい椅子が複数ある場合は、お知らせください。
○お申し込みは、インスタグラムのメッセージ or メールにてご連絡をお願いいたします。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2021/11/05
Yチェアの魅力とは?
家具の修理の仕事をしてきて、これまでに国産家具から輸入家具まで様々な家具の修理をしてきました。
それぞれの国、メーカーによって作り方にも特徴があります。
見た目は綺麗ですが、見えない所は大雑把に作っていたり、コストを抑えるために安い材料を使ったり、大量生産のためにスピード、効率を重視した、流れ作業で作っているんだろうな、と思える作り方をしていたり。
その中で、日本の家具とデンマークの家具はちゃんと作っている、という印象がありました。
日本の家具は「壊れないように」頑丈に作っていて、デンマークの家具はメンテナンスをすることを前提に作っている、というのもリペアの仕事をしていて感じたことの一つです。
また、デンマークの家具(特にウェグナーの家具)は作り方だけでなく、デザイン性、座り心地、機能性、丈夫さ、メンテナンスのしやすさなど色々な視点から見て、家具を作っているなと思います。
世の中には本当にたくさんの家具があります。
その中でも椅子は特に種類が豊富です。
数多くの椅子があり、修理をしたり、お店や雑誌で見たり、色々な椅子を見てきて、あえてNo.1を選ぶなら自分は「Yチェア」を選びます。
デザイン性、座り心地、丈夫さ、メンテナンスのしやすさ、価格、修理をするときのコスト…。
どれをとっても10点満点でいったら8点〜9点で、総合評価が高いです。
人それぞれに価値観があるので、好きなデザイン、好きなテイストを選ぶのは大事なことで否定はしません。
むしろこだわりがあってインテリアを楽しんでいる、お気に入りの家具を大事にしているということは、とても素敵なことだと思います。
ただ、何を買うか迷っている人、どんな椅子を買えば良いか分からない人にはYチェアをお勧めします。
Yチェアは少し白っぽいビーチ材や、色々な家具でも使われているオーク材、濃い色のウォルナット材、ヴィンテージに合うマホガニー材、カラー塗装された黒、白、グレー、緑、赤、青など、多くのラインナップがあるので、どの空間にも合わせやすい椅子です。
以前、築100年以上の日本の古民家に置かせていただいた時は、意外と赤がとても似合っていました。
そんなYチェアですが、1950年に北欧デザインの巨匠ハンス・J・ウェグナーがデザインし、カールハンセン&サンより発売されて以来、70年間途切れることなく作り続けられています。
これは裏を返せばどの世代にも、また色々な国でも受け入れられているということだと思います。
そしてそれは、次の世代にも受け継ぐことができる、ということでもあります。
受け継ぐことができるということは、家具のゴミが減ることにもつながります。
前職では大きな家具会社に勤めていたので、毎日ゴミ収集車4台分位の家具が捨てられている光景を目にしてきました。
1年だと、日本中だと、世界中だと、どれくらいの家具が捨てられているのかを想像すると言葉に詰まります。
捨てられている家具の多くは安価で大量生産されているものであったり、知らないメーカー、ブランドのものでした。
その多くの家具のゴミは最終的に燃やしたり、埋め立てられています。
Yチェアはデンマークの老舗家具メーカー、カールハンセン&サンの職人の方々により、受け継がれてきた技術、誇りを持って作られています。
また、細かい所を見れば見るほど、知れば知るほどウェグナーのこだわりを感じられます。
一生モノの椅子であり、次の世代に受け継ぐことができるYチェア。
まだまだお伝えしたい魅力がたくさんあるので、改めてブログに書こうと思います。
Tukuroi(ツクロイ)
愛媛県松山市三津1-2-8
カールハンセン&サン正規取扱店
北欧ヴィンテージ家具
家具修理
営業日:土曜日(11:00〜17:00)
定休日:日曜日
※平日は予約制になります。お気軽にご連絡下さい。
2021/09/28
「メンテナンス・リペア券」のご案内
こんにちは。Tukuroi(妻)です。
日頃から家具のメンテナンスやリペアのご相談をいただく中で、家具のお手入れをしたり手直しすることがまだまだ身近なことではないように感じます。
メンテナンスに対して不安をお持ちだったり、ご自分ですることにハードルを感じていたりする方が多いのではないかな、と思います。
ただ、家具を長く使う上で定期的なメンテナンスは不可欠です。
状態が悪くなる前に、日頃からメンテナンスをしてあげるとより長くお使いいただけると共に家具への愛着も増して、家具を長く使うことにも繋がると思っています。
そこで私たちが出来ることはないかなと考え、Tukuroiで家具を購入していただいた方に「メンテナンス・リペア券」を期間限定でプレゼントさせていただくことに致しました。
「メンテナンス・リペア券」について
□メンテナンス券
家具のメンテナンスを無料でしていただけます。
ソープメンテナンス・オイルメンテナンス・レザーメンテナンスの中からお選びいただきます。
□リペア券
家具を使用していく中でできてしまった、キズやシミなどのリペアを通常価格より50%OFFでしていただけます。
キズ修理・塗装塗り直し・グラつき修理・脚カットなど。
【注意事項】
・メンテナンス・リペアのどちらかよりお選びいただき、1点につき1回限り有効です。
(使用期限はございません)
・当店でご購入いただきました商品が対象となります。
・家具はお持ち込みしていただきますようお願いいたします。
※お持ち込みが難しい場合は、愛媛県内に限り配送も承ります。(別途送料を頂戴いたします)
・座面の張替に関してはデザイン、生地によっては対象外の場合もあります。お問い合わせください。
メンテナンスに関しましては、お預かりして私たちで行いますが、今後も自宅でやってみたい!自分たちで出来るようなりたい!という方がいらっしゃいましたら、一緒にレクチャーさせていただくことも可能です。
「メンテナンス・リペア券」は10月から配布を開始いたします。
配布期間は、2021年12月末までとなります。
「メンテナンス・リペア券」、その他家具のメンテナンスやリペアに関しましても、ご質問やお困り事がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さいませ!
2021/09/09
北欧の名作家具「OW149/コロニアルチェア」
こんにちは。Tukuroi(妻)です。
今回はお店で取り扱いのある家具についてのお話をさせていただこうと思います。
Tukuroiでは北欧のヴィンテージ家具の取り扱いと同時に創業113年、デンマークの老舗家具メーカー、カールハンセン&サン社の家具も販売しております。
夫婦とも北欧のヴィンテージ家具がもともと好きだったこともあり、お店を始める前はカールハンセン&サン社の家具について、深くは知りませんでした。
幸運なことに、Tukuroiで取り扱いをさせていただけることになり、実際に見て、触れて、使っていく中で、その素晴らしさを知りました。
(そして現在もデンマーク家具の歴史やデザインついて日々勉強です・・・)
古くから愛され続け、今もなお名作として高い人気を誇る北欧家具。
こちらのブログでも私たちが感じたことを中心に紹介していきたいと思っております。
そして今回は、1949年にオーレ・ヴァンシャーによりデザインされた「OW149/コロニアルチェア」をご紹介いたします。
【デザイナー、オーレ・ヴァンシャーってどんな人?】
「デンマーク家具デザインの父」と言われた、コーア・クリントの後継者と言える人物で、ヴァンシャーが52歳の時(1955年)、デンマーク王立芸術アカデミー家具科の教授にも選ばれています。
代表作の多くは、1940年~1950年代にかけて発表されており、師であるクリントの教えのひとつである「リ・デザイン」の手法を用い、気品あふれる作品をデザインしています。
家具デザイナーとしてばかりではなく、美術史学者の父の影響で、世界中の家具の歴史を研究し、本や論文を発表する学者としての一面もありました。
【OW149/コロニアルチェアってどんな椅子?】
デザイン
オーレ・ヴァンシャーがデザインした椅子の多くは「優雅」な雰囲気を持つものが多く、「OW149/コロニアルチェア」もまさに優雅という言葉がぴったりなアームチェアです。
その理由としては、細く緩やかなカーブを描くフレームのデザインにあると思います。
肘掛けの絶妙なカーブはついつい手を置きたくなってしまいます。
全体的に細く華奢なフレームですが、後脚の外側に向かうカーブなど、考え抜かれた構造により、安定性と強度を配慮したデザインとなっています。
そしてアームの先端の丸みや脚の先端のデザインなど、全体的に平面な部分がないことで、手触りだけでなく目にも優しいデザインです。
作り
オーレ・ヴァンシャーは、機械での量産を前提とした家具もいくつかデザインしており、その中のひとつとして「OW149/コロニアルチェア」がデザインされています。
優雅な雰囲気を保ちつつも、各部材を効率よく加工出来るように配慮されているのです。
例えば、座面と背もたれのレザークッションは、フレームに張り込むのではなく、置くだけの独立したデザインとなっています。
座面は、籐編みの四角い枠が独立した状態になっており、最終の組み立て段階でフレームにはめ込むことが出来るよう考えられています。
座り心地
レザークッションの中には、ウレタンチップとフェザーが使用されています。
フェザーだけでは沈み込みすぎる、ウレタンだけでは硬すぎる為、両方使用することで柔らかすぎず、硬すぎない絶妙な座り心地となっています。
身長158cmの私が座るとこんな感じです。椅子のような感覚で座ることが出来る反面、同種類のオットマンを一緒に使うとリラックスチェアとしてくつろいで座ることが出来ます。
体格に大きな差のある店主(189cm)が座るとこんな感じです。
【メンテナンスは?】
私たちも日々お店で家具のお手入れをしますが、「OW149/コロニアルチェア」は特にお手入れがしやすいと感じます。
ホコリやゴミが溜まりやすい隅の部分なども、クッション、籐編みの座面、全て取り外してお手入れが出来るからです。
普段は、パーツを取り外しながら埃をはらい、レザークッションは柔らかい布で乾拭きをしています。
レザークッションは、定期的に(半年~1年に1回程度)レザー用のクリーム等を塗って表面を保護してあげるとより長くお使いいただけると思います。
メンテナンスをしてあげないと、人間の皮膚と一緒で、レザーが段々と乾燥していき、ひび割れや破れの原因になってしまいます。
レーザークッションは、傷んでしまい使えない状態になった場合、メーカーにてクッション単品での購入が可能です。より安心してお使いいただけますね。
〈フレーム(木部)の汚れが気になった場合〉
汚れが深くない場合は、ソープメンンテナンスでお手入れし、仕上げにオイルを塗ります。
ソープメンテナンスとは・・・石鹸の泡で優しく洗い、汚れを取るメンテナンス方法です。
※木部が経年変化している場合、汚れている部分だけに行うと周りと色の差が生じる場合がございます。その場合は、広い範囲、または全体的に行うことをおすすめします。
デザインされて70年以上経つ名作「OW149/コロニアルチェア」。
私たちが「OW149/コロニアルチェア」を初めにご紹介したいと思ったのは、デザインや使い勝手はもちろんですが、長く使うことを考えた際にとても機能的に出来ているな、と感じたからです。
メンテナンスをしながら長く使い続けることで、家具への愛着が増していくと同時に、そんなお気に入りの家具に座って過ごす時間こそが、毎日をちょっと幸せにしてくれる大切な時間になるのではないかと思います。
今回ご紹介した「OW149/コロニアルチェア」は、Tukuroi店頭にてご覧いただけます。
その他の詳細は、「menu」画面の「contact」にてお問い合わせ下さいませ。
価格/¥343,200(税込)
仕様/オーク材・オイル仕上げ・ダークブラウンレザー(Thor306)
※展示入れ替えの為、展示品のみ10%OFFにて販売しております。
※同じ仕様のもので取り寄せの場合、納期は約5ヶ月程になります。
※オットマンは別売りになります。
2021/07/25
「欠けリペア」ワークショップを終えて

こんにちは。Tukuroi(妻)です。
夏は苦手な私ですが、長い梅雨が明けた頃、セミが鳴き出したのを聞いて、夏が来た!とはっきりと感じ、何だか嬉しくなりました。
長女の夏休みも始まり、それにしても毎日元気に遊んでいるので、感心してしまいます。
出掛けただけで疲れてしまうアラフォーの私は、せめて夏の暑さに負けないように、と体力作りの筋トレを始めてみました、、、笑
そんな夏の始まりに、第1回目のリペアワークショップを行いました。
内容は「欠けのリペア」。
6名の参加者のうち、5名はご自宅でお使いの家具を持ち込み、ご自身でリペアをされました。
お持ちいただいた家具は、チェストの引き出しを落としてしまった際にできた小さな欠けや、遊び盛りのお子さまがいらっしゃるお家で使われていて、たくさん欠けのあるソーイングワゴン。
ダイニングテーブルの天板をお持ちいただいた方も。
お話を聞いていると、皆さまそれぞれに思い入れがあり、大事に使われている家具たち。
これは満足してもらえる仕上がりになるよう、こちらもできる限りのサポートをしなければ!とさらに気合いが入りました。
そんなことを思いながら、いざ作業スタート。
それぞれ木の素材や仕上げ方法、傷の状態が違うため、今回は2通りのやり方をご用意し、その家具に合ったやり方で作業をしてもらいました。
2通りとは言え、状態によって作業工程はさまざま。
リペアを指導する店主は行ったり来たりで目まぐるしく動いておりました。
私も側で見ていて、家具リペアの奥深さを改めて感じました。
リペアを終え、仕上がった家具を見ながらお話しする中で、印象的だったこと。
それは参加者の皆さまがご自身で直した!という喜びに満ちていたことです。
もしかするとプロが直した方が更にキレイに仕上がったかもしれません。
しかし、そこでしか得られない「何か」をご自身でリペアをされる中で感じていただけたのではないかな、と勝手に思っています。
それは「達成感」なのか、「愛着」なのか。
人それぞれだとは思いますが、楽しかったです!と皆さまに言っていただけたことが、私たちは何よりとても嬉しかったです。
初のワークショップ。
そわそわとしている中で素晴らしく仕上がった家具たちの写真を撮り忘れるという大失態。
ぜひご紹介させていただきたかったです、、、
(ワークショップ途中の様子はいくつか添付いたしましたので、ご覧ください)
次回は家具を長く使うために必要なメンテナンスのワークショップを秋口にできたらな、と考えています。
少し先になりますが、詳細が決まりましたら、またお知らせいたします。